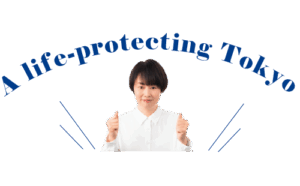2024年10月23日の公営企業会計決算特別委員会第二分科会の質疑で、特養ホームの水道料金についてとりあげました。
【私からのコメント】
コロナの影響や物価高騰によって、都民生活が厳しくなっている中、生活に欠かせない水道の料金負担の軽減として減免制度の拡充を委員会で求めてきました。
その中で、特養ホームの水道料金の負担が非常に大きいことを知りました。高齢者施設はもともと低い介護報酬と、コロナの影響から抜け出せないまま、物価高騰が追い打ちをかけ、経営が厳しい状況になっている事業者が少なくありません。
大事な社会資源を支えるために、都として何ができるのかを考え、今回の「共同住宅扱い」の拡充の質問を作ることにしました。この制度自体はとても重要な制度ですが、本来であれば制度の対象になっていて、家庭生活用水の低廉化を図ることができるはずが、そうはなっていない部分の改善を求めました。
質問を作る際には現場で働く方々に状況をお聞きしました。引き続き、現場の実態や声をきいて取り組んでいきたいと思います。
令和5年度の水道料金収入はどうだったか、評価をうかがう
福手委員 日本共産党の福手ゆう子です。資料の提供、ありがとうございました。
では、質問をしていきます。
水道料金の収入はコロナ禍で大きく減りましたが、令和4年度決算では徐々に回復してきているという状況でした。
令和5年度の水道料金収入はどうだったのでしょうか。評価と併せて伺います。
長嶺総務部長 令和5年度の給水収益は約3110億円であり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大きく減少した令和2年度より前の水準におおむね戻っております。
福手委員 令和2年度のコロナ前の水準にまで料金収入が回復してきたという答弁でした。
内訳を見ても、ホテルなどの大口利用が戻ってきていることが分かります。経済活動の再開で、コロナ前の状況にほぼ回復したといえる一方で、いまだコロナの影響から抜け出せないまま物価高騰が重なり、暮らしや経営の困難が深刻化している方たちがいます。
私の地元文京区では、区内で26年間、特養ホームの運営をしてきた事業者が、コロナ禍、厳しい経営が続き、とうとう今年度末に撤退することを決めました。また別の高齢者施設も、やはりコロナがきっかけで、20年以上続けてきた介護サービスの提供を終了しました。
地域の社会資源である高齢者施設の閉鎖や撤退は、住民の間に不安が広がり、同時に、どうにかならなかったのかという声も多く聞かれました。
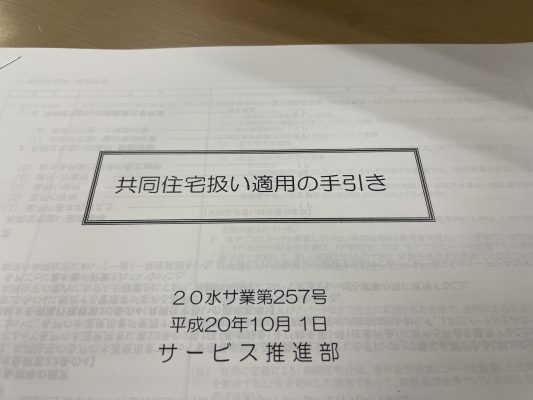
デイサービス事業所が水道料金減免の対象となっている理由をうかがう
社会福祉施設の水道料金について伺っていきたいと思います。
水道局は、社会福祉事業を実施する上で水道料金の負担が大きい施設に対して水道料金の減免をしています。
高齢者のデイサービス事業所が社会福祉施設減免の対象となっている理由を伺います。
荒畑サービス推進部長 当局が行っております社会福祉施設減免は、社会福祉法の適用を受ける社会福祉事業のうち、同法第二条第二項各号または同条第三項第二号から第十一号までに規定する事業でありまして、相談支援等や、国または地方公共団体の経営するもの等を除いたものに適用しております。
老人デイサービス事業は、社会福祉法第二条第三項第四号に規定される事業であることから、この対象となっております。
福手委員 デイサービス事業所は、社会福祉事業を行う施設として社会福祉法に定められています。社会福祉施設が事業を行う上で水道料金の負担が大きく、その負担を抑えることが必要であるため、減免されています。
しかし、どの社会福祉施設でも減免されるわけではなく、先ほどの答弁のように、相談支援事業所などは対象外になっています。
ただ、単独では対象外の福祉施設であっても、特養ホームやデイサービス事業所のように減免の対象である施設と併設になっている場合は、水道メーターが一緒であっても減免になります。しかし、店舗と併設している場合は、店舗は社会福祉施設ではないため、メーターも分けていなければ特養ホームも減免にならなくなります。つまり、社会福祉施設かどうかで判断をしています。
「共同住宅扱い」が適用されると特養ホームの水道料金はいくらになるか
25人が入所する特養ホームで、呼び口径40ミリ、2か月で620立方メートルの水を利用した場合
では、減免制度とは別で、特養ホームなどの入所施設の水道料金負担を大幅に軽減する方法として共同住宅扱いというのがあります。
水道料金は、使用量が多くなるほど料金単価が高くなる料金体系になっています。そうすると、例えば共同住宅で住戸一つ一つに水道メーターがついておらず、共同住宅の建物で一つの水道メーターが設置されている場合は、全体の使用量が多くなります。水道料金が物すごく高くなってしまいます。
こういう場合に、水道局は共同住宅扱いという料金の計算方法を適用することで、全体の使用量を各入居者が均等に使用したものとして計算し、その合計額を共同住宅の所有者が一括で支払うというやり方で、半分近く料金が安くなります。各戸に水道メーターがある世帯の水道料金の負担と比べても、同等のレベルにすることができます。
そして、この共同住宅扱いは、特養ホームも当てはめることができます。
では、具体的にお聞きします。
呼び口径40ミリで、2か月で620立方メートルを25人が入所する特養ホームで使用し、社会福祉施設減免が適用された場合、通常の計算方法では水道料金は幾らになりますか。
荒畑サービス推進部長 社会福祉施設減免を適用した場合の水道料金を試算いたしますと、約19万6000円でございます。
福手委員 では、今と同じ条件で共同住宅扱いで計算した場合は、水道料金は幾らになりますか。
荒畑サービス推進部長 同様に、25世帯の特別養護老人ホームに共同住宅扱いを適用すると仮定した場合の水道料金の試算額は、約7万円でございます。
福手委員 共同住宅扱いが適用されると、料金が19万6000円から約7万円に大きく引き下げられます。いい換えれば、これだけの差が生じている料金負担を公平化し料金の低廉化を行うことで都民生活を支える意義ある対応だと改めて確認することができました。
令和5年度の共同住宅扱いの適用件数の実績を伺います。
荒畑サービス推進部長 令和5年度末における共同住宅扱いの適用件数は、約1万4000件でございます。
福手委員 昨年度は約1万4000件。詳しくお聞きしましたら、区部では1万1947件、多摩では2487件が適用され、件数の推移は、例年同じくらいで大きく変わることはありませんでした。
特養ホームとデイサービスが合築だと共同住宅扱いは適用されないのは不合理
適用基準の見直しの検討が必要ではないか
都内の、ある特養ホームの責任者の方にお話を伺ったところ、施設が共同住宅扱いの適用になっていて大変助かっていると話されていました。また、幾つかの特養にお聞きをしたところ、不適用で使っていない、共同住宅扱いについて知らないという返事が多くありました。
介護施設の経費で、人件費の次に重いのが固定費、水道代といわれています。ネット検索をすると、軽減方法についていろいろアドバイスする、そういう記事もあり、その中には水道局の共同住宅扱いも書かれていました。水道料金の負担は、介護施設の運営で大きな課題になっているということが分かります。
共同住宅扱いの適用の手引には、どういう場合に適用、適用外になるかが書かれています。適用事例には、寮、宿舎、特別養護老人ホームの場合というのがあり、その注意書きには、特別養護老人ホームについては、通所介護事業での水使用は家事用に該当しないとあります。
つまりこれは、共同住宅扱いとは水道を家事用に使用していることが条件であるため、特養ホームにデイサービスが併設されていて水道メーターが別々になっていない場合は適用外になってしまうということです。私は、これは改善するべきだと考えています。
特養ホーム単独の施設なら共同住宅扱いで水道料金が半額以下になるのに、デイサービスと合築だと適用されないというのは、非常に不合理だと思います。
給水条例がつくられたのは昭和33年。当時、特養ホームを住宅とみなして共同住宅扱いの対象としてきたことは、とても重要な判断だったと思います。ただ、当時つくられた基準で今も続けていくと、軽減できるはずの特養ホームが軽減できなくなっています。
通所介護、デイサービスは1979年に始まり、介護保険制度が始まった2000年以降、15年間で全国の事業所数が大きく増えています。そういう中で、特養ホームにデイサービスを併設する施設も増えたと考えられます。
時代の変化に合わせて、共同住宅扱いの特養ホームの適用基準を見直す検討が必要ではないでしょうか。伺います。
荒畑サービス推進部長 共同住宅扱いは、料金負担の公平化を図ることを目的といたしまして、料金算定における特例として実施しているものでございます。
社会福祉施設の減免制度とは趣旨が異なるものであることから、見直しは考えておりません。
福手委員 共同住宅扱いの目的は、料金負担の公平化を図るためといわれました。先ほどの手引には、家庭生活用水の低廉化を図るためとも書いてあります。減免と共同住宅扱いは趣旨が違うとおっしゃいますが、どちらも社会福祉施設の料金負担について対応しているものであることには違いはありません。
デイサービスなどの社会福祉施設は、店舗とは違います。店舗が入っている施設も認めてほしいといっているわけではなく、あくまでも限定的な部分での検討を求めているんです。
施設で生活する高齢者が食事をしたり、お風呂に入ったりして家庭用として水を使い、生活する上で、水道代は必ずかかる経費になります、しかも、金額が大きいので、軽減できるかどうかは施設にとって大きなことですと、施設の運営者が話していました。
施設が既に建っている状態から、水道メーターを入所施設とデイサービスの施設とで分けるのは難しく、そうなると、結局、共同住宅扱いは諦めるしかありません。
これから施設を建設するというときに、必ず地元自治体や東京都の福祉局施設支援課に相談に行くようになっていますので、せめて、こうしたところで漏れなく共同住宅扱いについてお知らせするよう、局から働きかけていただきたいと思います。そうすることで、逆にメーターを別々にした方がランニングコストが軽減できるという判断ができます。周知の強化をお願いしたいと思います。
ただ、しかし、それでも解決しない問題があります。入所施設とデイサービスの施設で水道メーターを分けたとしても、入所者と通所利用者の食事をつくる厨房は、普通、施設には一つだけです。厨房を入所者とデイサービス用に分けて二つつくるということは、恐らく、どの事業者もそれはしないと思います。
メーターを分けるだけではなくて、厨房などの設備もそれぞれ分けなければ、共同住宅扱い、つまり水道料金の公平化はできないということならば、本来は使えるのに、使えない、諦めてくださいということになってしまいます。やっぱり制度が実情に合っていないのではないでしょうか。
特養ホームの水道料金の負担が重い現状に対して、共同住宅扱いが非常に有効な解決手段となっていますので、本来軽減される施設が適用となるように、共同住宅扱いの基準を新しい事情に適用させることが求められています。ぜひ検討していただくことを改めて求めて、次の質問に移ります。